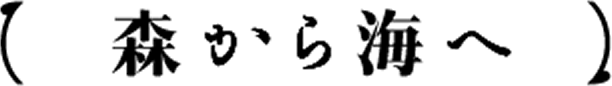ニホンジカによる生態系への影響
全国でニホンジカ(以下、シカと表記)の数が増えています。 シカはこれまでは、低山や人里近くに生息し、 おもに農林業に被害を与えていました。 農業をまもるために、柵を作ったり、 田畑周辺で駆除を行っていました。 ところが、近年シカは森の奥や標高の高い山岳地帯に進出し、 高山植物を食べたり、森林の幼木や下草を食べるようになりました。 樹木の皮を食べて樹木を枯らすようになりました。 そのために、草原や森で生活していた昆虫や鳥が 生活できないような状況になってきました。 シカは生態系、特に、森の生態系、多くの動植物に大きな影響を 与えるようになってきたのです。大型獣と共存してきた日本
小さな島国の中に多くの人口をかかえ、 工業を発展させた国でありながら、 ヒグマやツキノワグマ、シカ、カモシカ、 イノシシなどの大型の哺乳類が 生き続けていることは、特筆すべきことです。 同様の特徴を持つイギリスなどにはないことです。 日本人は、これらの動物と、時には農業を守るために激しく闘い、 狩猟などで食料としながら、 また一方で彼らを絶滅させることなく共存してきました。 ニホンオオカミやニホンカワウソなどを 絶滅させる失敗も経験しながら、 日本の生物多様性はかろうじてある水準で守られてきました。
シカの数をコントロールする
現在のシカの増加は、生態系に強い影響を与えています。 このまま放置すれば、多くの動植物が滅ぶ可能性さえあります。 また、森を失えば、私たちの生活の基盤である きれいな水を失い、さらに土砂崩落などによる 人身被害の可能性もあります。 従って、増えすぎたシカの数を減らす必要があります。 このために、環境省や農水省などの 行政が民間団体と協力しながら対策を始めています。 一方で、シカも生態系の一員であり、 生態系の中でもいくつかの役割をもっています。 従って、シカを絶滅させないようにしなくてはなりません。 残念ながら、現代の科学ではシカの適正な数を 導き出すことはできません。 生態系への影響をモニタリングしながら、 影響の出ない程度に数を減らすしかありません。